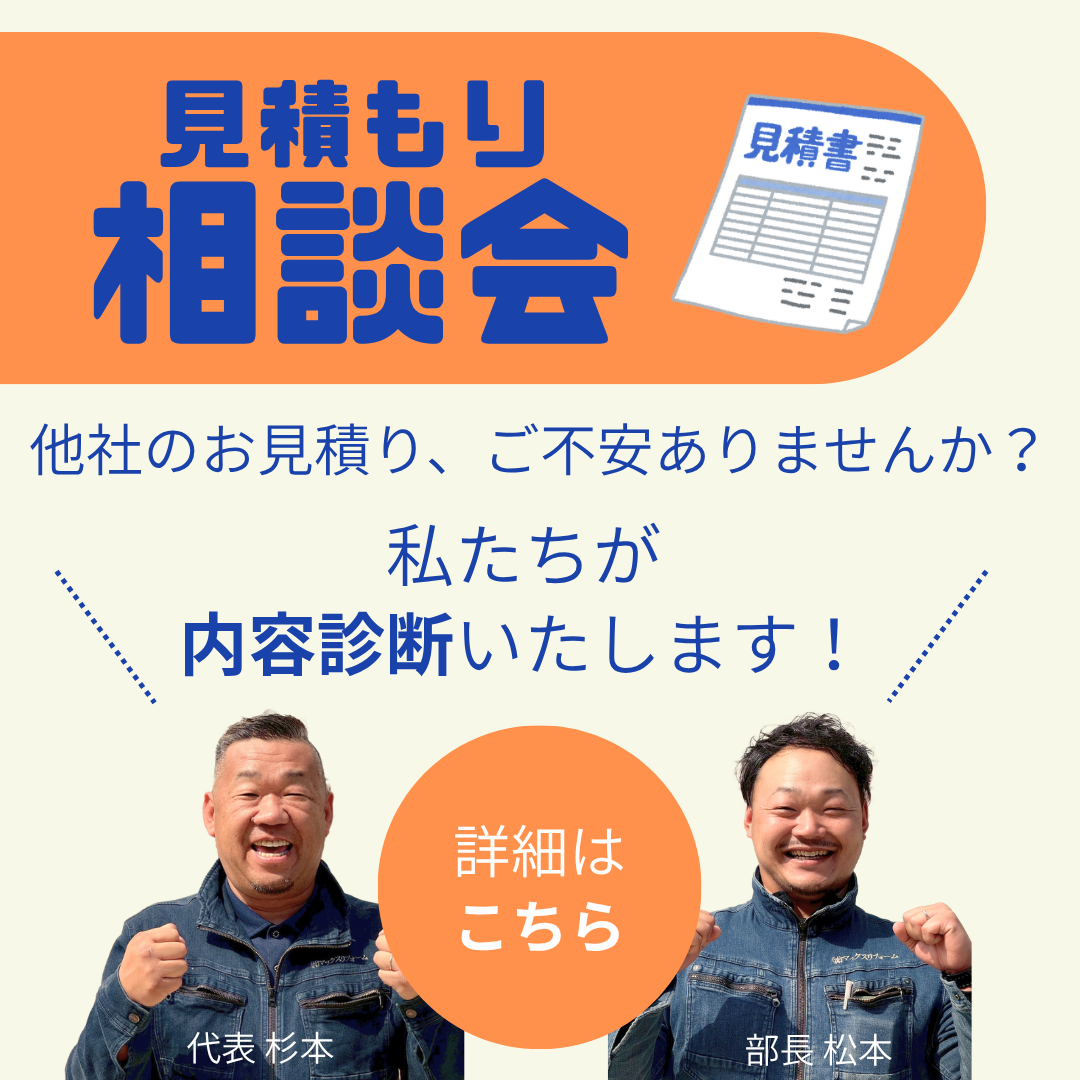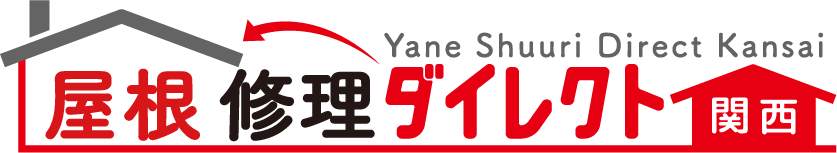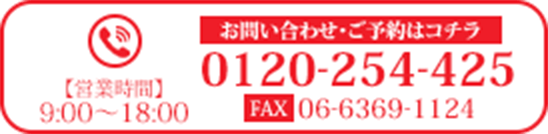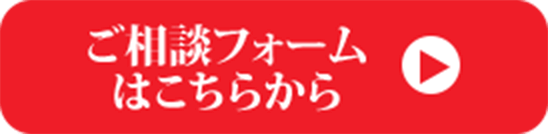屋根の笠木とは?役割・修理方法・費用相場・メンテナンスのポイント

はじめに
屋根の「笠木(かさぎ)」は、普段あまり意識されることのない部材ですが、雨漏りを防ぐために非常に重要な役割を果たしています。
しかし、笠木が適切に設置されていなかったり、経年劣化で傷んでしまうと、建物内部への水の浸入を引き起こし、大きな修理が必要になることもあります。
本記事では、笠木の基本的な役割、材質、よくある不具合とその修理方法、費用相場について詳しく解説していきます。
また、トラブルを未然に防ぐためのメンテナンスのポイントについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください(^^)/
1. 笠木とは?
笠木(かさぎ)とは、手すり・塀・腰壁・屋上のパラペット(立ち上がり部分)などの最上部に設置される仕上げ材のことを指します。建物の防水性能を向上させ、美観を保つ役割を持っています。
1-1. 笠木が設置される場所
笠木は以下のような場所に使用されます。
- 屋根のパラペット(立ち上がり部分)
- ベランダやバルコニーの手すり壁の頂上部分
- 階段の手すりや室内の腰壁の仕上げ材
- 建物の外壁や塀の最上部
2. 笠木の役割
笠木には大きく3つの役割があります。
2-1. 防水性の確保
笠木は、建物の最上部に位置するため、雨水が直接当たります。そのため、防水性を高めることが求められます。もし笠木が劣化してめくれたり、隙間ができると、そこから雨水が侵入し、建物内部での雨漏りが発生する原因になります。特に、シーリング材の劣化や釘の浮きによって生じる隙間は、雨水が侵入しやすいポイントです。これを防ぐためには、定期的な点検と防水処理のメンテナンスが不可欠です。
2-2. 躯体(くたい)を守る
笠木の下には、建物の構造部分(躯体)があります。特に屋上やベランダのパラペット部分は、外部環境の影響を受けやすく、劣化しやすい箇所です。適切な笠木を設置することで、雨水の侵入を防ぎ、躯体を守ることができます。また、風や紫外線によるダメージから建物を保護し、耐久性を向上させる効果もあります。
2-3. 美観の向上
笠木には建物の見た目を整えるという役割もあります。特に外観のデザインを重視する場合、笠木の材質や形状が建物全体の印象を大きく左右します。意匠性の高い笠木を採用することで、住宅の価値を高めることも可能です。
▶笠木とは?その役割とメンテナンスについて~劣化のサインと修理方法~
3. 笠木の材質
笠木の材質には以下のようなものがあります。それぞれの材質には寿命やメンテナンス方法が異なりますので、特徴を理解して適切に対処することが重要です。
3-1. 木製笠木
寿命:10~20年
劣化サインと原因
- 表面のひび割れ、変色、腐食が見られる
- 雨水を吸収しやすいため、カビやコケが発生する
- 乾燥と湿気の繰り返しにより、ひび割れや反りが発生する
メンテナンス方法
- 防水塗装を定期的に施し、湿気による劣化を防ぐ
- ひび割れや腐食が進んだ場合は、部分交換または補修を行う
- 防腐剤を塗布し、耐久性を向上させる
3-2. 金属製笠木(ガルバリウム鋼板・ステンレス・アルミ)
寿命:20~40年
劣化サインと原因
- 錆びや腐食が見られる(特に傷がある部分)
- 接合部のシーリングの劣化により雨水が侵入する
- 強風や衝撃で固定用のビスが浮く、抜ける
メンテナンス方法
- 定期的に防錆塗装を施し、錆の進行を防ぐ
- シーリング材の劣化をチェックし、必要に応じて再施工する
- 固定ビスの状態を確認し、ゆるみがあれば締め直す
▶笠木板金のトラブルと対処法~錆びやひび割れ、雨漏りなどの解決策~
3-3. モルタル・セメント製笠木
寿命:20~30年
劣化サインと原因
- ひび割れや崩れが発生する
- 雨水がしみ込むことで内部の鉄筋が錆び、膨張し、さらなる劣化を引き起こす
- 風化により表面が粉状になってくる
メンテナンス方法
- ひび割れが見つかった場合は、早急に補修材で埋める
- 防水塗装を定期的に施し、雨水の浸入を防ぐ
- 劣化が激しい場合は、上から金属製カバーを設置する補強工事を行う
各材質ごとに異なる特徴を理解し、適切なメンテナンスを施すことで、笠木の寿命を延ばし、雨漏りなどのトラブルを防ぐことができます。
定期的な点検を怠らず、早めの対策を心がけましょう(*^^*)
4. 笠木の不具合と修理方法
4-1. よくある不具合
笠木にはいくつかの不具合が発生しやすく、特に以下の点が問題となります。
1. 経年劣化による錆びや腐食(特に金属製笠木)
金属製の笠木は耐久性が高いものの、長年雨風や紫外線にさらされることで、徐々に劣化していきます。特に、塗装が剥がれた部分や傷がついた箇所から錆びが発生し、それが進行すると腐食によって穴が開くことがあります。錆びがひどくなると、強度が落ち、風による飛散や変形の原因にもなります。
対策と修理方法
- 定期的に塗装を施し、防錆加工をする
- 錆びが軽度の場合は、研磨して防錆塗装を施す
- 穴が開いてしまった場合は、パッチ補修または部分的な交換を行う
2. シーリングの劣化による雨水の侵入
笠木の継ぎ目や接合部にはシーリング材が使用されており、これが劣化すると隙間ができ、雨水が侵入する原因となります。特に、長年の紫外線や温度変化によってシーリングが硬化し、ひび割れたり剥がれたりすると、防水機能が大幅に低下します。
対策と修理方法
- 3〜5年ごとにシーリングの状態を確認し、劣化していたら打ち替える
- ひび割れが見つかったら、補修材を充填して早めに対処
- 防水性能を向上させるため、シーリングの打ち直しとトップコートの追加を検討
⇩⇩【施工事例】雨漏り修理!屋上の笠木補修で防水性を向上⇩⇩
3. 固定用の釘やビスの浮き・緩み・抜け
強風や地震の影響で、笠木を固定している釘やビスが緩んだり浮いたりすることがあります。これを放置すると、固定が不十分な状態になり、最悪の場合、強風で笠木が飛散する可能性もあります。
対策と修理方法
- 定期点検で釘やビスの状態を確認し、緩んでいる場合は締め直す
- 強風が多い地域では、ビスを増し締めする、または耐久性の高い固定材を使用する
- ビスの固定が甘い場合は、補強プレートを追加する
4. 笠木の浮きや変形
建物の経年劣化や地震、強風の影響で笠木自体が浮いてしまったり、変形してしまうことがあります。浮きが発生すると、そこから雨水が入り込み、雨漏りの原因となります。
対策と修理方法
- 定期的に接合部の状態を確認し、浮きが見られる場合は固定を強化
- 軽度の浮きであれば、ビスや接着剤で固定し直す
- 変形が著しい場合は、部分的な交換を検討する
5. 笠木のひび割れや破損(特にモルタル・セメント製)
モルタルやセメント製の笠木は、経年による乾燥収縮や外的要因によってひび割れが発生しやすいです。ひび割れが進行すると、雨水がしみ込んで内部の鉄筋が錆び、さらに劣化を加速させることになります。
対策と修理方法
- ひび割れを早めに発見し、防水材や補修材で埋める
- 風化が進行している場合は、表面のモルタルを塗り直す
- ひび割れが大きい場合は、補強ネットや金属カバーを取り付けて補強する
4-2. 修理方法と費用相場
| 修理内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 笠木の交換(部分補修) | 1万円~10万円 |
| 笠木が原因の雨漏り修理 | 10万円~30万円 |
| シーリング補修 | 1万円以下 |
| ビス・釘の固定 | 1万円以下 |
▶笠木修理の費用相場は?笠木のめくれ、剥がれを放置すべきでない理由
5. 笠木のメンテナンスと災害対策
笠木の定期点検の重要性
笠木は建物の防水性能を維持し、雨漏りや躯体の劣化を防ぐために重要な役割を果たしています。しかし、風雨や紫外線の影響を受けやすく、放置しておくと劣化が進行し、修理費用が高額になることがあります。定期点検を行うことで、早期に不具合を発見し、適切な対策を講じることが可能です。
定期点検のチェックポイント
✅笠木表面の状態:変色、錆び、ひび割れ、塗装の剥がれがないか確認。
✅シーリングの劣化:継ぎ目や接合部のシーリング材にヒビや剥がれがないかチェック。
✅固定状態の確認:釘やビスが緩んでいないか、固定がしっかりされているか。
✅雨水の侵入:笠木周辺に雨水がしみ込んだ跡がないか、内壁に雨染みがないかを確認。
✅隙間や浮きの確認:強風や地震で笠木が浮いていないか、接合部に隙間ができていないか。
▶ベランダからの雨漏りの原因は笠木にあり!確認すべきポイントと修理方法
点検頻度の目安
- 屋外にある笠木(屋上・ベランダ・バルコニー):3年に1回以上
- 屋内の笠木(階段・腰壁):5年に1回程度
- 台風や地震の後:被害がないか早急に確認
5-2. 笠木の具体的なメンテナンス方法
1. 笠木の塗装メンテナンス
対象:木製・金属製の笠木
笠木の表面塗装は、雨や紫外線の影響で徐々に劣化します。塗装が剥がれると、木製の場合は腐食しやすくなり、金属製の場合は錆びが発生する可能性が高まります。
メンテナンス方法:
- 3〜5年ごとに塗装の再施工を行う
- 防水性の高い塗料を使用する(ウレタン塗装・シリコン塗装など)
- 塗装前に表面の汚れや錆を除去する
2. シーリング材の補修
対象:全ての笠木(特に金属・モルタル・セメント製)
シーリング材は、気温の変化や紫外線の影響で劣化し、硬化してひび割れが発生します。これを放置すると、隙間から雨水が侵入し、躯体を劣化させる原因になります。
メンテナンス方法
- 劣化したシーリングを撤去し、新しいシーリング材に打ち替える
- 高耐久性のシーリング材(変成シリコン・ウレタン系)を使用する
- 定期的にシーリング部分の状態を確認し、小さなひび割れでも補修する
3. 固定金具やビスの点検・交換
対象:金属製・木製の笠木
釘やビスは、長期間の使用により緩みや抜けが生じることがあります。固定が甘くなると、強風や地震時に笠木が浮いたり、最悪の場合飛散する可能性もあります。
メンテナンス方法
- 定期的に固定金具やビスの緩みをチェック
- 錆びたビスは交換し、ステンレス製や防錆処理されたビスを使用
- 釘の増し打ちや補強プレートを使用して固定強度を向上
5-3. 災害対策としての強化メンテナンス
近年の台風や地震による被害が増えているため、笠木の耐久性を向上させる対策が重要です。
1. 強風対策
- 笠木をしっかり固定するため、ビスの本数を増やし、強化プレートを使用する
- 金属製笠木には、接着剤を併用してさらに固定強度を高める
- 台風の前後にビスの状態をチェックし、緩みがあれば増し締めを行う
2. 防水性強化
- 笠木の継ぎ目部分に追加の防水テープを施工
- 既存のシーリング部分にトップコートを塗布し、耐久性を向上させる
- 雨漏りが発生しやすい箇所には防水シートを追加
3. 地震対策
- 笠木の固定に柔軟性のある材料を使用し、揺れに強い構造にする
- モルタルやセメント製笠木は、補強ネットを追加して割れにくくする
- 金属製笠木の場合は、耐震金具を使用して固定を強化する
6. 火災保険を活用した修理方法
6-1. 笠木の損傷は火災保険で修理できる?
台風や地震などの自然災害によって笠木が破損した場合、火災保険を活用して修理できるケースがあります。火災保険は火事だけでなく、風災や雪災、水災などの被害も補償対象となることが多く、屋根の笠木の破損も保険の適用範囲に含まれることがあります。
▶火災保険で屋根工事ができるケースとできないケースの違いを知っておこう!
6-2. 火災保険適用の条件
火災保険で笠木の修理費用を補償してもらうためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 自然災害による損傷であること
- 台風や強風、地震、大雪などの影響で笠木が破損した場合
- 物が飛来し、笠木が損傷した場合(飛来物被害)
- 雨漏りの原因が災害による笠木の破損と認められた場合
- 経年劣化ではないこと
- 自然災害ではなく、単なる経年劣化による損傷は保険適用外となるケースが多い
- ただし、経年劣化と災害の複合的な要因と判断される場合、部分的に適用されることもある
- 被害発生から一定期間内に申請すること
- 一般的に、被害発生から3年以内に申請しなければならない
- 早めに申請し、確実に補償を受けることが重要
▶急増する屋根修理トラブル!火災保険に便乗した勧誘には要注意!
6-3. 火災保険申請の手順
火災保険を利用して笠木の修理を行う場合、以下の手順を踏む必要があります。
① 被害状況の確認と写真撮影
まずは、笠木の破損状況を詳細に確認し、写真を撮影します。撮影時のポイントは以下の通りです。
- 笠木の破損部位を近くから撮影する
- 破損した周囲の状況も含めて撮影する
- 建物全体の写真も撮り、災害による影響を明確にする
- 撮影日時が分かるようにする
② 修理業者に見積もりを依頼
信頼できる屋根修理業者に相談し、被害状況の調査と見積もりを依頼します。
- 火災保険の申請に対応した業者を選ぶ
- 破損の詳細と修理内容を明記した見積書を作成してもらう
- 保険会社へ提出するための書類準備を依頼する
③ 保険会社に連絡し、申請書類を提出
保険会社に被害状況を報告し、申請書類を提出します。
- 必要書類(被害写真・見積書・申請書)を準備
- 保険会社の担当者が現地調査を行う可能性がある
- 申請後、審査が行われ、結果が通知される
④ 保険金の支給と修理の実施
申請が承認されると、保険金が支給されます。
- 支給された保険金を活用し、修理を実施
- 修理完了後、報告書を提出する場合もある
6-4. 火災保険を活用する際の注意点

1. 申請期限を守る
火災保険には申請期限があるため、被害発生後すぐに申請を行うことが重要です。放置すると、補償が受けられなくなる可能性があります。
2. 修理業者の選定に注意
火災保険を利用した修理を装った悪徳業者によるトラブルが発生しています。
- 「自己負担なしで修理できる」と勧誘してくる業者には注意
- 適正な見積もりを作成し、実績のある業者に依頼する
3. 事前に保険内容を確認
契約している火災保険の補償内容を事前に確認し、適用条件や補償範囲を把握しておくことが大切です。
まとめ
笠木の役割や修理方法について詳しく解説しました。
定期的な点検を行い、早めのメンテナンスを心がけることで、建物の耐久性を向上させることができます。
特に台風や強風の後は、火災保険を活用して修理費用を軽減する方法も検討してみましょう(^^)/
お問い合わせ情報
屋根に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお気軽にどうぞ!
- 電話番号:0120-254-425
- メールアドレス:info@maxreform.co.jp
- お問い合わせフォーム:こちらをクリック
- 公式LINE:LINEでお問い合わせ
- 無料点検ご予約カレンダー:こちらをクリック
- Zoom相談ご予約カレンダー:こちらをクリック
株式会社マックスリフォーム
所在地: 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-24 フェスタ江坂401
電話番号: 0120-254-425
施工対応エリア: 関西全域
公式サイト: https://maxreform.co.jp/
私たちの専門チームが、あなたのお家のスレート屋根のメンテナンスを全力でサポートいたします。お問い合わせをお待ちしております!