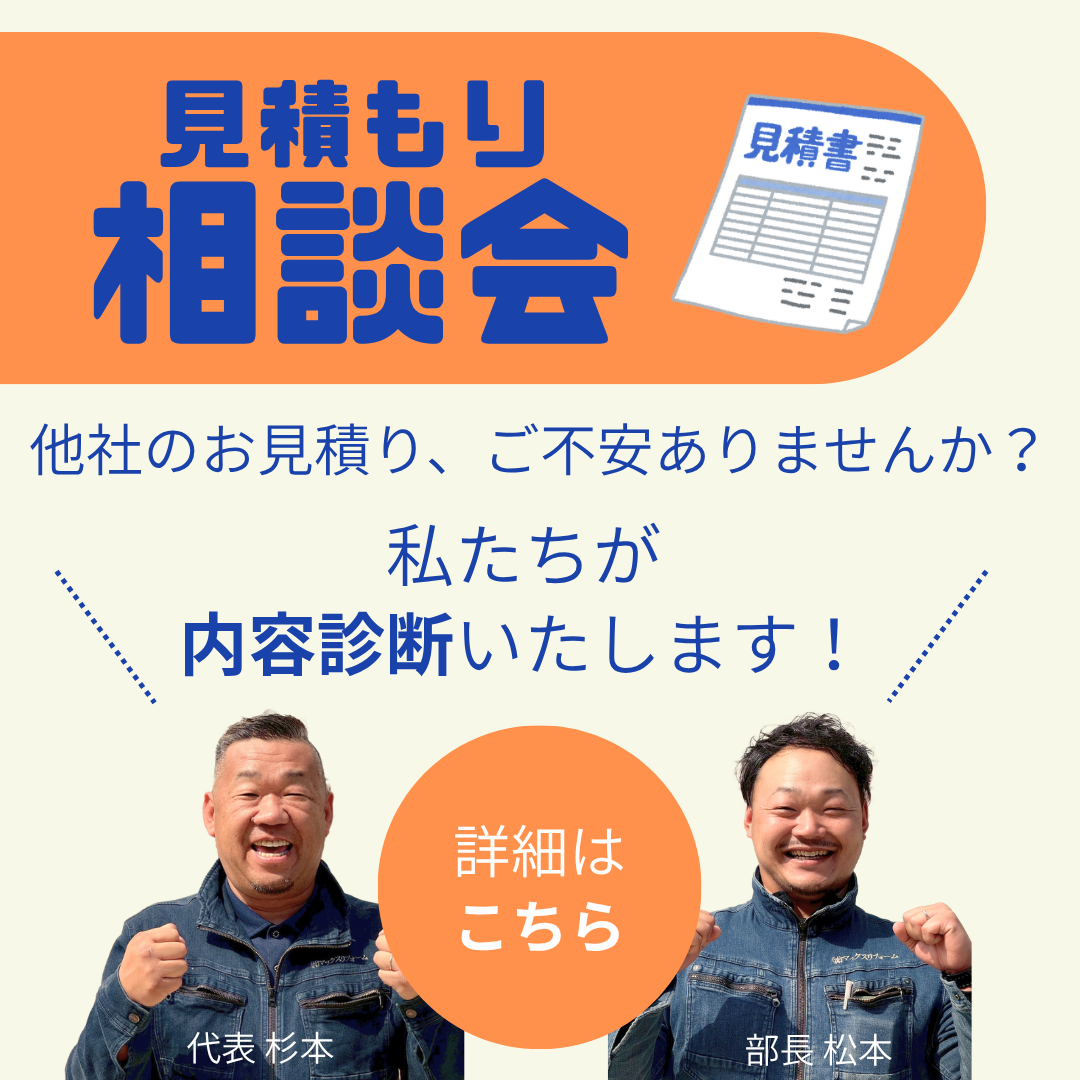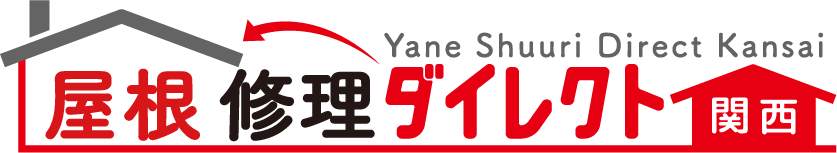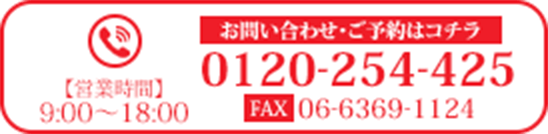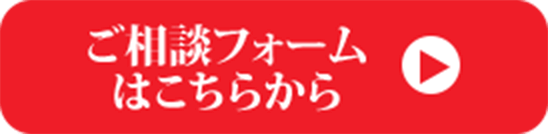屋根の強度を決める!垂木サイズと屋根材の関係を徹底解説

屋根の下に隠れた存在でありながら、建物全体の安全性と耐久性に大きく関わっている「垂木(たるき)」。
普段は目にすることがない部分ですが、屋根の強度や寿命を左右する重要な役割を果たしています。
適切なサイズや素材の垂木を選ばなければ、屋根の歪みや雨漏りの原因となり、建物全体に悪影響を及ぼすことも…。
この記事では、垂木の基本知識から屋根材ごとの最適なサイズ、そしてメンテナンス方法まで詳しく解説します。
これを読めば、屋根の見えない部分にも安心を確保するための知識が手に入るはずです!
屋根の内部構造を知ろう
屋根は見た目以上に複雑な構造で成り立っています。普段は屋根材しか目にすることがありませんが、その下には家全体を守るために設計されたさまざまな構造要素が隠れています。この屋根内部の仕組みを理解することは、メンテナンスや修理を行う際に非常に重要です。
- 屋根材(仕上げ材)
- まず、最も外側にあるのが屋根材です。瓦、スレート、ガルバリウム鋼板など、建物に応じた屋根材が使用されます。この層は直接雨風や日光を受けるため、定期的なメンテナンスが不可欠です。
- まず、最も外側にあるのが屋根材です。瓦、スレート、ガルバリウム鋼板など、建物に応じた屋根材が使用されます。この層は直接雨風や日光を受けるため、定期的なメンテナンスが不可欠です。
- 防水シート(ルーフィング)
- 屋根材の下には防水シート(ルーフィング)が敷かれています。これは二次防水の役割を果たし、屋根材から浸入した雨水を防ぎます。劣化すると雨漏りのリスクが高まるため、点検が必要です。
- 屋根材の下には防水シート(ルーフィング)が敷かれています。これは二次防水の役割を果たし、屋根材から浸入した雨水を防ぎます。劣化すると雨漏りのリスクが高まるため、点検が必要です。
- 野地板(のじいた)
- 防水シートの下には野地板があります。野地板は屋根材と防水シートを支える役割を担い、合板や構造用合板が使用されることが一般的です。この部分が劣化すると、屋根全体の強度が低下します。
- 防水シートの下には野地板があります。野地板は屋根材と防水シートを支える役割を担い、合板や構造用合板が使用されることが一般的です。この部分が劣化すると、屋根全体の強度が低下します。
- 垂木(たるき)
- 野地板を支えるために設置されているのが垂木です。垂木は屋根の骨組みとして、屋根全体の荷重を分散し、安定性を確保します。適切なサイズや配置でなければ、屋根のたわみや崩壊のリスクが高まります。
- 野地板を支えるために設置されているのが垂木です。垂木は屋根の骨組みとして、屋根全体の荷重を分散し、安定性を確保します。適切なサイズや配置でなければ、屋根のたわみや崩壊のリスクが高まります。
- 母屋(もや)・梁(はり)
- 垂木の下には母屋や梁が設置されており、建物全体の骨組みを強化しています。これらの構造材がしっかりと設置されていないと、屋根全体が不安定になります。
- 垂木の下には母屋や梁が設置されており、建物全体の骨組みを強化しています。これらの構造材がしっかりと設置されていないと、屋根全体が不安定になります。
- 断熱材
- 屋根の内部には断熱材が敷かれていることが多く、特に寒冷地や夏場の暑さ対策として重要です。断熱材が適切に機能していないと、室内の温度管理が難しくなります。
- 屋根の内部には断熱材が敷かれていることが多く、特に寒冷地や夏場の暑さ対策として重要です。断熱材が適切に機能していないと、室内の温度管理が難しくなります。
- 通気層
- 屋根の構造には通気層が設けられることが一般的です。これにより湿気を逃がし、結露の発生を防ぎます。通気層がないと、内部に湿気がたまり、カビや腐食の原因となります。
このように、屋根は複数の層と構造材で成り立っており、それぞれが建物を守る重要な役割を果たしています。
特に垂木は、これらの構造の中核を担い、屋根の安定性と強度を保つために欠かせない存在です。
屋根の問題を早期に発見し修理するためには、この内部構造を理解することが大切です(^^)/
垂木の役割とは?
垂木(たるき)は屋根の構造を支える重要な建材です。
野地板の下に配置され、屋根全体の荷重を支える役割を果たします。
具体的には、屋根の最も高い位置にある「棟木(むなぎ)」と、軒先にある「桁(けた)」の間に取り付けられる長い木材で、屋根面の形状や強度を決定づけます。
垂木がしっかりと設置されていないと、屋根面が歪み、雨漏りや風害のリスクが高まります。
特に三角屋根の家では、垂木が屋根の形状と安定性を保つために不可欠な存在です。
また、垂木の配置や素材が不適切な場合、屋根のたわみや劣化を早める原因となることがあります。そのため、適切な垂木の選定と施工が重要です。
垂木の基本的なサイズ・寸法
垂木の寸法は、屋根材や設計条件によって異なりますが、一般的な標準寸法は以下の通りです:
- 標準的な屋根(スレート屋根・ガルバリウム鋼板など)
- 幅:4.5cm
- 高さ:6cm
- 瓦屋根
- 幅:6cm
- 高さ:7.5cm
さらに、軒の出(屋根の端が外壁よりどれだけ突き出しているか)が長くなる場合、垂木の寸法は追加の強度が求められるため、以下のように変化します:
- 軒の出が長い場合(スレート屋根など)
- 幅:4.5cm
- 高さ:7.5cm
- 軒の出が長い場合(瓦屋根)
- 幅:6cm
- 高さ:10.5cm
垂木の寸法を正しく選定することで、屋根の強度を保ち、長期間にわたり安定した状態を維持することが可能になります。
▶屋根材によって垂木のサイズは変わる?屋根工事の基礎知識を知っておこう!
垂木の寸法が変わる理由
垂木の寸法が変わる最も大きな理由は、屋根材の「重さ」です。
スレートやガルバリウム鋼板といった軽量な屋根材に比べて、瓦屋根ははるかに重くなります。
屋根材の重さ
瓦屋根
瓦屋根は、日本の伝統的な屋根材として人気がありますが、その重さは1㎡あたり約40~60kgに達します。
この重量は屋根全体に大きな負担をかけるため、強度の高い垂木が必要です。瓦の重みをしっかり支えるため、垂木には十分な幅と高さが求められます。
適切な垂木を使用しないと、屋根全体が沈み込み、構造的な問題を引き起こすリスクがあります。
スレート屋根
スレート屋根は軽量で施工がしやすく、1㎡あたりの重さは約20kgです。
瓦屋根に比べて軽いため、垂木にかかる負担も少なく、標準的な寸法の垂木で十分対応できます。
しかし、軽量であるがゆえに強風などでの浮き上がりリスクがあるため、しっかりとした固定が重要です。
ガルバリウム鋼板
ガルバリウム鋼板は最も軽量な屋根材の一つで、1㎡あたりの重さは約5kg程度です。
その軽さから耐震性に優れ、建物への負担が少ないのが特徴です。
このため、比較的細めの垂木でも十分ですが、薄い分、防音性や断熱性には注意が必要です。
このように屋根材ごとに重さが異なるため、それぞれの特性に応じた垂木の選定が必要です。
適切な垂木を選ばないと、屋根全体が沈み込み、雨漏りやひび割れの原因になることがあります。
軒の出の長さ
- 軒部分は、垂木だけで屋根材と野地板を支えるため、支点がない分、垂れ下がるリスクがあります。軒の出が長いほど、このリスクは高まります。
- そのため、軒の出が長い場合には、垂木の高さを増して強度を補強します。特に瓦屋根の場合、軒の出が長いと大きな荷重がかかるため、垂木の高さを10.5cmにして補強します。この補強を怠ると、軒先部分が下がり、雨水が逆流して雨漏りを引き起こす可能性があります。
垂木の間隔と荷重分散
- 垂木の強度だけでなく、その配置間隔も重要です。標準的な住宅では、垂木の間隔は約30cm〜45cm程度に設定されます。
- 重い屋根材の場合、垂木の間隔を狭めることで荷重を分散させ、全体の強度を高めることもあります。また、垂木の間隔が広すぎると、屋根のたわみや振動が増加し、屋根材の破損リスクが高まります。
垂木の種類と素材

垂木には、使用される木材の種類や加工方法によってさまざまなバリエーションがあります。
それぞれの素材には特徴とメリット・デメリットがあります。
無垢材垂木
- 自然の木材をそのまま使用したものです。
- 強度が高く加工しやすいですが、反りや割れのリスクがあります。また、湿気に弱く、適切な防水処理が必要です。
集成材垂木
- 小さな木片を接着剤で接合して作られた木材です。
- 反りや割れに強く、安定した品質を保てます。無垢材に比べて耐久性が高く、均一な強度を確保できますが、接着剤の劣化には注意が必要です。
垂木のメンテナンスと寿命
垂木は建物の内部構造材であるため、普段は目にすることがありませんが、屋根の耐久性に大きく関わる重要な部分です。適切なメンテナンスを行うことで、垂木の寿命を延ばすことができます。
- メンテナンスのポイント
- 雨漏り:垂木が濡れると腐食やカビの原因になります。特に無垢材の場合、水分を吸収しやすく、劣化が早まります。
- シロアリ被害:木材部分にはシロアリ被害のリスクがあります。定期的な点検と防虫処理が効果的です。
- たわみ・変形:屋根材の重みで垂木がたわむことがあります。これにより屋根面が波打ち、見た目の悪化や雨漏りを引き起こします。
- 寿命の目安
- 無垢材垂木:約30〜40年
- 集成材垂木:約40〜50年
- 金属製垂木:50年以上
定期的な屋根点検を行い、問題があれば早期に修繕することが大切です。特に築20年以上の建物では、垂木の状態を確認し、必要に応じて補強や交換を検討しましょう。
知っておきたい!屋根の劣化サインと早期発見のポイント

屋根の劣化は放置すると大きな修繕費用につながることがあります。
しかし、適切な時期にメンテナンスを行えば、被害を最小限に抑えることができます。ここでは、屋根の劣化サインと早期発見のポイントを詳しく解説します。
屋根材の色褪せや変色
- 屋根材が日光や雨風にさらされることで、徐々に色褪せや変色が起こります。これは塗膜の劣化のサインであり、防水性が低下している可能性があります。
屋根材の浮きや剥がれ
- 強風や地震の影響で屋根材が浮いたり剥がれたりすることがあります。これを放置すると雨水が侵入し、下地材や垂木の腐食を引き起こします。
雨漏りやシミの発生
- 天井や壁にシミが現れた場合、すでに雨漏りが進行している可能性があります。特に垂木や野地板の劣化が原因であることが多いため、早急な点検と修理が必要です。
苔やカビの発生
- 屋根の表面に苔やカビが発生している場合、屋根材の防水性が低下していることを示しています。特に湿気が多い地域では注意が必要です。
早期発見のポイント
- 定期的な目視点検:年に1~2回、自宅の周囲から屋根の状態を確認しましょう。
- 悪天候後のチェック:台風や大雨の後は特に念入りに確認することが重要です。
- 専門業者による点検:5年に一度程度は、専門業者による詳しい点検を依頼しましょう。
記事の要点まとめ

- 垂木の重要性:垂木は屋根の構造を支える中核的な役割を担い、屋根の強度と耐久性に大きく影響します。
- 屋根材と垂木の関係:屋根材の重さに応じて垂木のサイズを調整する必要があり、特に瓦屋根のような重い屋根材には強固な垂木が求められます。
- 垂木の寸法調整:軒の出の長さや屋根材の種類により垂木の寸法を変えることで、屋根全体の安定性を保ちます。
- メンテナンスの重要性:定期的な点検とメンテナンスを行うことで、垂木や屋根全体の劣化を防ぎ、建物の寿命を延ばすことができます。
- 専門家の点検推奨:屋根の安全性を確保するためには、専門家による定期的な点検と適切な修繕が不可欠です。
屋根は定期的に点検しておきましょう
屋根は日々、雨風や紫外線にさらされており、知らず知らずのうちに劣化が進んでいます。
しかし、屋根の上は普段目にすることがないため、小さな不具合や損傷を見逃してしまいがちです。
定期的な点検を行うことで、重大なトラブルを未然に防ぐことができます(*^^*)
なぜ定期的な点検が必要なのか?
- 早期発見がコスト削減に繋がる:小さなひび割れや剥がれも、放置すると雨漏りや構造材の腐食に発展し、高額な修理費用が必要になることがあります。早期に問題を発見することで、最小限の補修で済む場合が多いです。
- 屋根の寿命を延ばせる:点検を行い適切なメンテナンスを実施することで、屋根の寿命を大幅に延ばすことができます。特に垂木や野地板などの内部構造の劣化を防ぐことが重要です。
- 安全性の確保:瓦や屋根材の浮きや剥がれは、強風時に飛散する危険があります。定期的な点検で安全性を保ちましょう。
点検のタイミングは?
- 築10年目が最初の目安:新築から10年経過した頃が最初の点検の目安です。それ以降は5年ごとに点検を行うのが理想的です。
- 台風や大雪の後:強い風や積雪の後は屋根材がズレたり、破損していることがあります。天候の影響を受けた直後は点検をおすすめします。
- 周囲の建物の改修時:近隣で足場を組む工事がある場合、そのタイミングで自宅の屋根の点検を依頼するのも効率的です。
専門家による点検をおすすめします

屋根の点検は高所作業を伴うため、危険が伴います。
専門業者に依頼することで、安全にかつ正確な点検が可能です。
また、専門家は目視だけでは見つけにくい内部の劣化も見逃しません。
私たち株式会社マックスリフォームでは、屋根の無料点検を行っております。屋根の状態が気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
お問い合わせ情報
屋根に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお気軽にどうぞ!
- 電話番号:0120-254-425
- メールアドレス:info@maxreform.co.jp
- お問い合わせフォーム:こちらをクリック
- 公式LINE:LINEでお問い合わせ
- 無料点検ご予約カレンダー:こちらをクリック
- Zoom相談ご予約カレンダー:こちらをクリック
株式会社マックスリフォーム
所在地: 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-24 フェスタ江坂401
電話番号: 0120-254-425
施工対応エリア: 関西全域
公式サイト: https://maxreform.co.jp/
私たちの専門チームが、あなたのお家のスレート屋根のメンテナンスを全力でサポートいたします。お問い合わせをお待ちしております!